社会人博士に限らず、会社派遣制度はやはり選抜のハードルが高いものです。。。
Nekoace も、会社派遣で社会人博士課程に進学しましたが、なかなか苦しんだ挙句、おそらくかなりのウルトラCで解決しました。 再現性は置いといて、一事例として共有します。
それは、少しでも博士派遣を実現する可能性を高めるために、自分で立ち上げたプロジェクトチームの活動の一環として自分自身の博士進学を組み込む、という手法を取りました。この時の行動記録です。
今回の記事のポイントはこちら
- 「社会人博士課程に興味がある方」「サラリーマンでももっとハードワークできるぞ!と感じている方」に対してケースを提供すること
- 会社のルールは使おうとしてもなかなか上手くいかないもの
- 色々なことをやりながら、使えるものはなんでも使って実現にもっていく
- 自分の裁量で自分の博士進学を承認するという裏技の紹介
会社から博士進学の許可が出ない時にどうするか?
皆さんは会社の中で ”やりたいけれど難しい” ことを実行するためには何が必要だと考えていますか?
- ひたすら上司に希望を伝え続けますか
- やりたいことができる組織に移動しますか
- それとも、こっそり始めてしまいますか
いずれも正解だと思います。Nekoは会社の派遣制度を使って社会人博士に進学しましたが、社内でやりたいことを通すには時にタフな交渉能力が要求されます。 私が置かれた状況と解決策を具体的に書いていきます。


志望者のいない会社派遣制度
Nekoaceが当時勤めていたのは日系の大手電機メーカーです。
こういった会社の例にもれず、大学院派遣が制度として存在していました。
この制度では、会社の業務に貢献できる研究内容であれば社会人博士に社費で進学できるというものでした。 その場合、会社からは3年間の学費と、相談次第ですが、会社の業務として平日に研究を行うことができました。
社会人4年目頃でしょうか。
私は入社当初からこの制度を知っており、また初めての国際学会発表で刺激を受けた こともあり、本格的に制度利用の検討を始めていました。
同時に、周囲にも進学希望を伝えて、反発も受けながら(笑)、外堀を埋めていきました。
運がよかったことにこの時の上司の一人がアカデミア出身の方で、博士進学に対してとても前向きに協力してくれました。
しかしよくよく調べていくとこの制度は研究所内でも特定の部署でしか適用実績が無いことが分かりました。 これは、組織の長い歴史によるのですが、もともと基礎研究色の強い部署で主に運用されていた制度で、私がいた応用研究色の強い部署では事例が無かったのです。
この頃には応援してくれている上司と一緒になってなんとか進学できる方法がないか検討していました。 指導教員と出会ったのはこの頃です。 前回の記事で簡単に紹介しています。
解決策を模索する日々
さて、進学予定の研究室は決まったものの、大きな二つの問題を解決する必要がありました。
- 1つ目は、現在の部署に博士進学の制度が無いこと。
- 2つ目は、制度利用するとして博士進学が会社に利益をもたらすことを説明し承認を得ること。
解決策を模索する日々の始まりです。
これまで社会人博士課程に進んだ社内の方に伝手を頼ってヒアリングしました。
また、進学予定の研究室とはできる範囲で研究の構想を練りました。
実験に慣れる意味もあり、少しずつ研究を開始し、学会発表の予定も組みました。
そのうちに、1つ目の問題は無理くりですが解決できる道筋が見えてきました。
現在の部署に制度が無いのなら、制度がある部署に異動してしまう、ということです。 ただ、その場合、博士進学に向けてこれまでにしてきた準備をしっかりと異動先の新しい上司に説明する必要があり、異動先の選定を始めていました。
2つ目の問題に関しては、異動先の部署のミッションと、進学予定の研究室の研究領域が重複して、かつ、会社に貢献できるストーリーを構築する必要がありました。 こういった、研究とは関係ないような調整仕事で疲れはて、半ば諦めかけていたころに吉報が舞い込みます。
突然道が開けた ”発想の転換”
ある日突然、私が所属していた部署が部署ごと他の部門に移管されることが決まったのです。
しかも移管先は研究部門で、かつ博士派遣の制度利用の実績があったのです! 嘘のような話ですが、これで1つ目の「制度の問題」は一気に解決しました。
問題は2つ目です。
私の会社では、特定の技術や製品に関するプロジェクト単位で仕事が進みます。 博士進学は特定のプロジェクトに紐づいて実現できるのですが、そのプロジェクトに研究成果を反映することが前提です。
企業研究所あるあるですが、研究成果を業務にどうつなげるか、がすごく難しいのです。 だって、数十年後に役立つような研究をしても会社の役に立たないし(基礎物理学とかでしょうか、例えば)、すぐ使えるような研究だと会社の強みにならないからイマイチです。
そして、研究を遂行している方と、その研究を統括している方だと視点が違うので、認識違いのようなミスマッチが起きるのです。


そんなときに、これまたちょうどよいタイミングなのですが、私が所属していたプロジェクト(つまり博士進学の箱にしようとしていたプロジェクト)のプロジェクトリーダーが異動となり、空席となりました。これが二つ目の問題の解決策になりました。
この瞬間になかなか進学できずうんうん唸っていた頭にウルトラC的解決策が浮かびます。
つまり、
博士進学を予定している自分がプロジェクトリーダーになって自分で自分に進学許可を出せばいい!
と思ったんです。”発想の転換”です。
結局のところ、担当メンバーが博士課程に進みたいと思っても、プロジェクトリーダーがOKと言わなければ実現しないわけです。 そして、それぞれの熱意に温度差があると、やはりコミュニケーションロスが発生してうまくいかないのです。
だから、
自分がプロジェクトリーダーとなってプロジェクト全体の進捗管理をしつつ、
テーマメンバーとして、一部タスクを担いつつ、
プロジェクト自体の基礎研究能力向上策として、自分の博士進学を承認すればよい
と思いました。
幸いにして、博士課程の進捗準備やらで、マルチタスクの訓練はひたすら実践していたので、
プロジェクトリーダー&業務担当&博士学生のトリプルワークもなんとかこなせるだろうと考えました。
段々、ブラック感出てきましたね(笑)
結果的には、後にこれにビジネススクールが入ってくるのでさらに慌ただしくなっていきますが、それはじきに書きます。
(参考までに私の会社は世間的には定時で帰れて福利厚生も揃ったホワイト企業なので、ブラックに働いている人は自主的に自分を追い込んでいる少数の人間に限られますので。)
さて、スキームは以下です。
プロジェクトリーダーとしては、数人の部下を持ちました。 そして、プロジェクト全体の方向性を会社の方向性と合わせ、それぞれの部下と業務目標を設定します。 自分自身は、業務目標として博士課程での研究を個人目標として設定しました。 このスキームで関連部署と上司説明を行い了承を得ることができました。 当時、6年目でのプロジェクトリーダーとなり、周囲ではおそらく最年少でした。


プロジェクトリーダーとなると、自分のプロジェクトの予算策定の権限が与えられます。 私の場合は数名のプロジェクトでしたので、大体500-1000万円程度の予算で、その中の200万円程度を自分向けの予算として確保しました。
博士進学の制度を利用するにあたり、自分自身の学費と大学との共同研究費、さらに各種研究費をこの中から捻出することができました。
さて、プロジェクトマネジメントというと、若い方はまだ馴染みが薄いかもしれません。でもこの分野は珍しく、理論体系がしっかりしていて、学べば必ず役立つ領域。幾つか参考図書貼っときますのでご興味あったらどうぞ。
ついに博士課程に入学できた!
こういった経緯で、紆余曲折ありましたが、無事に会社の制度で社会人博士課程に進学することができました。
学生時代に一度博士進学は諦めましたが、その後社会人博士という制度があることを知り、会社に入ってからも博士課程の制度を狙い続け、学会発表や部署異動といったチャンスに食らいつきなんとか、社会人7年目の時に社会人博士となりました。
すでに30歳を過ぎていましたが、ついに念願かない感無量でした。博士課程入学後の話は次の話で。
この辺りの話好きな人はこういう本好きかもなので置いておきます。
中村先生の反骨精神が良く分かります。解説するのも野暮なのでこれはもう読んでみてください。
さて、最初に書いた通りこの話はN=1の極めて再現性に乏しいものです。
それでもあえてこのブログで書いている理由は一つだけ。
持ちうるあらゆる手を使って目標達成に向けた努力をすることの大切さを伝えたい
からです。
このブログを読んでいる方は、社会人大学院というものに興味ある方が多いのだろうと思います。そんな意志を持つ皆さんは、今後必ず苦労します。なぜなら、「普通」で無いからです。
日本の会社に入社する/しているならば特に、目立つ存在は煙たがれる場合が過半です。それはもうしょうがないのです。
しかし、普通でないことは悪いことでは決してない。何か大きなことを成し遂げるかもしれない。だからこそ、そんな方には、自分が今持つすべてのカードを使って目的達成する努力をいとわないでほしいのです。
そういう姿、きっと周りにも伝わりますからね。
もし、なかなか思い通りに行かなくて、何から始めればいいか分からなくなった時には英会話から始めてみたらいいと思います。社会人の場合は、短期で一気に習得した方が何かと良いので、専属の日本人コンサルタントの助けも借りて最短で会話力を磨けるBizmatesがおすすめです。英語はやればやるだけ進むので、出来るところから前進しましょう!
まとめ
今回は、会社派遣の精度を使い、社会人として博士課程に入学するところまでを書きました。
制度を使うまでに様々なことがありましたが、結局、自分でプロジェクトを立ち上げ、プロジェクトの方向性と自分が博士探求したい分野と紐づけ、自分の裁量の中で自分の博士としての研究活動を推進していく、というプロセスを取り、時間はかかりましたが、社会人博士として入学できました。
企業の制度を使うと余計な苦労もありますが、メリットも大きい制度ですので、利用できるならばするべきです。皆様のご健闘を!
今日はここまでです。それでは。
Nekoaceは社内起業が専門ですが、そのために必要な社内政治と合わせてノウハウを詰め込んだnoteを書いています。ご興味ある方は無料部分だけでもどうぞ。
社会人やりながら博士(工学)、専門職(技術経営、MOT)卒業した大学も有料で公開しています。ご興味ある方はあわせてどうぞ。















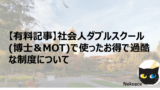




コメント